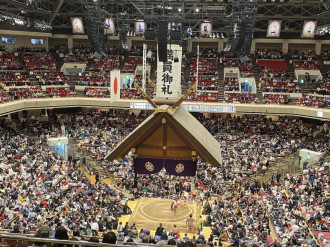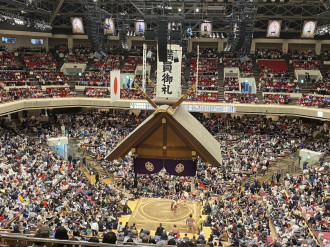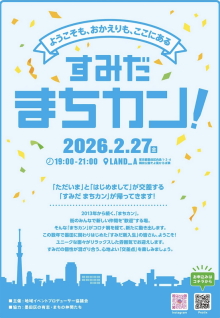インタビュー 「すみだ活性化のキーパーソンが語る墨田と私」
東武タウンソラマチ 北川亮社長(前編)
すみだ経済新聞では、「ひと つながる 墨田区」を象徴する企画として、地域で活躍するキーパーソンへのリレーインタビュー「すみだ活性化のキーパーソンが語る『墨田と私』」を展開しています。
今回は、墨田区で観光まちづくりの中核を担う東武タウンソラマチ・北川亮社長にインタビュー。13周年を迎えた東京スカイツリーとスカイツリータウンのこれまでの歩みについて、お話を伺いました。

【1】社長就任後に見えた「人」の風景
すみだ経済新聞:4月に社長に就任されたとのことですが、実際に働いてみて変化はありましたか?
北川社長:私はオープン前からずっと東武タウンソラマチにいまして、会社ができた半年後くらいに配属されて以来、課長、部長、本部長、そして昨年は常務を務めていました。なので「安全・安心な施設運営」という根幹は10年以上やってきたことと変わらないんですが、社長になると“見え方”がまったく変わりました。
課長や部長の頃は“自分がきちんと業務をこなす”ことが中心だったんです。でも社長になると、“それを担ってくれている社員一人ひとりのモチベーション”や、“生活”まで含めて気にかけなければいけないな、と。当社の社員だけではなく、業務委託で働いている会社の方々の環境も含めて、全体を見ていかなければと思うようになりました。
だから、「安全・安心な施設運営」という根幹は同じなのに、これまでとは見える風景が違う。13年目を迎えてもまったく飽きることなく、むしろ役職が上がった分だけ、“もっと良くしたい”という思いが強くなりました。新鮮な気持ちで、4月からまた一歩踏み出している感覚です。
【2】仕事も子育ても、思い出の場所は墨田
すみだ経済新聞:墨田区にはもともと馴染みがあったのですか?
北川社長:実は、私は千葉出身なんですが、2006(平成18)年に結婚したタイミングで墨田区石原に引っ越したんです。そこから10年ほど住んでいました。ちょうどその頃に子どもも生まれて、幼稚園から小学校3年生くらいまで、この地域で育ちました。
職場も墨田区内でしたし、住まいも墨田。子育ての記憶も墨田。だから“思い出”といえば、自然と墨田に結びつくんですよね。
例えば、近くに住んでいた友人の伝手(つて)で、花火大会の日にマンションの屋上から家族で花火を見せてもらったこともありました。地域のお寺のご住職ともご縁があって、その息子さんと子どもが同級生だったりと、地域と深くつながっていた実感があります。
今は別の場所に住んでいますが、仕事ではずっと墨田ですし、地元の友人もたくさんいます。もう、墨田は“愛着”のある場所ですね。
【3】変わらぬ運営方針 安全・安心を第一に
すみだ経済新聞:東京ソラマチの運営において、特に大切にしていることはありますか?
北川社長:やっぱり“事故を起こさない、安全・安心な施設運営”がいちばん大事だと思っています。これは私だけじゃなくて、歴代の社長もずっとそうだったと思います。
施設で何か事故があれば、お客さまの信頼は一気に失われますし、当然来館者数も減ってしまいます。だから、“いつ来ても安心できる場所”であることを、何よりも優先して考えています。
例えば、花火大会などでたくさんのお客さまが来られるとき。運営ノウハウは蓄積されていますが、最近は急な雨もありますし、予想を超える人出になることもある。そういったときに、“どうやって安全にご案内するか”ということを、常に想定しています。
すみだ経済新聞:実際に運営面で取り組まれている工夫はありますか?
北川社長:地味ですが、当社と東武タワースカイツリー社の社員が毎週交代でゴミ拾いをしながら近隣をまわっています。これ、あまり知られていないんですけど、地域の方々にも“いつもきれいにしてますね”って言っていただけることがあって、ありがたいですね。
あと、東京ソラマチには各出入り口に“カウンター”が設置されていて、入館した人数と退館した人数を常にリアルタイムで計測してるんです。館内にいる人数が一定数を超えると、“混雑して危険かもしれない”という判断をして、入場制限をかけたりもします。これは開業当初からやっている取り組みで、今でも最新のシステムに更新しながら活用しています。
閉館時間のエレベーター稼働も、あえて少しゆっくりにして、お客さまが慌てて出ていかなくてもいいように工夫していたりもします。細かいことの積み重ねですが、そういう“気づかれない安全・安心”の取り組みをしっかり支えていきたいと思っています。

【4】13年間で変わらぬ信念「オールターゲット」
すみだ経済新聞:スカイツリータウン開業から13年。印象に残っている出来事や、転機となった瞬間はありましたか?
北川社長:開業時のことは、今でもはっきり覚えています。グランドオープンは2012年5月22日だったんですが、その1週間ほど前から“東武カード会員やテナントさんのお得意さまを招いたプレオープンが続いていました。
その期間が本当に大変で。例えば“明日はこの入り口からこの人たちをお迎えして、ここからお帰りいただく”というような計画を毎晩立てて、深夜に帰ってまた翌朝すぐ出社する。その繰り返しでした。開業日を無事終えたときは、もう“やっと終わった”という感覚で、いわゆる身内でグランドオープンのお祝いらしいこともないまま、次の日の業務に入っていましたね(笑)。
でも今振り返ると、“楽しかったな”と思います。まるでまちづくりゲームをリアルでやっているような感覚でした。次々に予想外のことが起こって、それをその場でどんどん判断して解決していく。性格的にも、そういう“短期勝負型”が合っていたんだと思います。
すみだ経済新聞:施設として成長し続けてきた理由は、どこにあると思いますか?
北川社長:いろんな要因がありますけど、開業当初から“オールターゲット”でやってきたのがすごく大きかったと思っています。地域の人、観光客、ファミリー、外国人、近隣の県からの小旅行の方――“みんなが対象”。それがブレなかった。
途中で“若者に特化しよう”とか“ファミリー層中心に”というようなことはせず、最初から“誰でも楽しめる場所”をめざしてやってきた。それが結果的に、多くの人に愛されて、持続的な来場につながっているんじゃないかなと。
実は、開業当初は「オールターゲットって誰でも言えるよね」って、どこかで思っていた部分もあったんです。でも年月がたつにつれて、“本当にそれを実行し続けている場所って、意外とないかもしれない”って気づいた。いま思えば、あれが大きな“ターニングポイント”だったのかもしれません。

(写真提供=東京スカイツリータウン広報事務局)
【5】観光と日常が交わるまちへ
すみだ経済新聞:東京ソラマチという場所は、観光拠点である一方で、地域住民にとっての日常の場でもあります。そのバランスについて、どのように考えていらっしゃいますか?
北川社長:今まで申し上げてきた通り、観光と地域、どちらに寄せるかといったことはあまり意識していないんです。施設の運営方針として、ずっと“オールターゲット”でやってきているので、観光のお客さまに向けての仕掛けもあれば、地域の方に楽しんでいただけるイベントもある。どちらか一方に偏ることなく、自然に“フラットに”対応しているという感覚です。
例えば、お店の入れ替えがあるときには、“どんな業態が必要か”“今のラインナップとのバランスはどうか”といった視点で全体を見ます。「若者向けにしよう」とか「観光客向けにしよう」という特化した戦略ではなく、あくまで“みんなが楽しめる空間”を前提にしています。
このスタンスは、これからも変えないつもりです。どんな属性の方でも、「なんかここ、自分の居場所みたいだな」と思ってもらえる場所でありたい。実際、近隣の方たちの中には、「東京ソラマチは、もう自分の場所だよ」って言ってくれる方もいるんですよ。そういう声が、本当にうれしいですね。
<インタビュー後編へ>
インタビュー:長尾 円
撮影:宮脇 恒